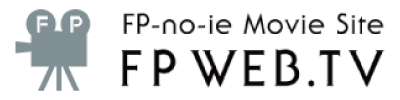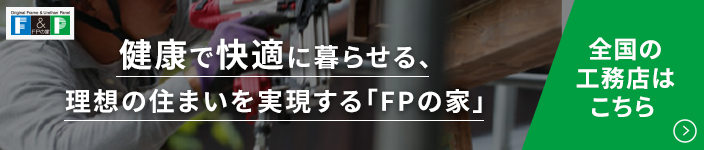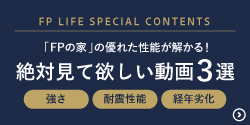日本で注意すべき災害といえば真っ先に浮かぶのは地震かと思いますが、最近は豪雨による水害も増えており、ここ数年各地で起こっている被害を記憶する方も少なくないでしょう。
災害に強い住宅づくりでは、水害に対する備えも必要不可欠です。
今回のコラムでは、豪雨災害に備え、水害の影響を受けにくい住宅について解説します。
豪雨や水害が起こったときに被害を少しでも軽減し、速やかに復旧してできるだけ早く元の生活に戻れるのはどんな住宅か考えてみましょう。

目次
近年の水害状況、水害による住宅への影響をチェック
「最近、豪雨や水害のニュースが多い気がする」と感じている方、その印象は当たっています。
地球温暖化やヒートアイランド現象の影響で、豪雨災害が増加しているのです。
気象庁の観測データの統計によると、日本で1時間に50mm以上(滝のように降る非常に激しい雨)の豪雨の発生回数は年々増加傾向にあり、2011~2020年での10年間で平均年間発生回数は約334回。
統計開始時の1976~1985年の平均年間発生回数は約226回なので、1.5倍にもなっています。
さらに国土交通省の「河川事業概要2021」によると、2008年~2017年の10年間では全国の約97%以上の市町村で水害・土砂災害が発生していることがわかります。
日本では、ほとんど毎年のように豪雨による水害や土砂災害が起こっている状況です。
多数の行方不明者や死者が発生した「令和2年7月豪雨」や「令和2年台風第10号」なども、記憶に新しいのではないでしょうか。
令和2年7月豪雨
令和2年(2020年)7月の豪雨は記録的な大雨で九州南部、九州北部を中心に、東海、東北地方にも甚大な被害をもたらしました。
死者・行方不明86名、住家被害は約16,600棟となり、多数の避難者や集落の孤立も発生しました。
令和2年台風第10号
令和2年に発生した台風10号は、九州を中心に暴風、大雨、高波、高潮などが発生。
猛烈な風や非常に強い風を観測し、観測史上1位の値を超えるなど記録的な暴風雨となりました。
死者・行方不明は6名。
九州を中心に広い範囲で停電のほか、家屋被害、全壊・半壊39戸などの被害がありました。
豪雨や河川の氾濫で床上浸水してしまったら、部屋だけでなく家具や家電、住宅設備なども水びたしになってしまいます。
水が引いたあとは残った泥の掃除や消毒が必要です。
家電や家具、住宅設備は水に浸ってダメになってしまいますし、床下や壁に水が浸透して建物自体の建て替えが必要になってしまうことも。
同じ地域で同様の被害を受けている住宅が多くなるので、復旧や修繕、建て替えのための人員や職人が不足し、元の生活に戻るまでに長い時間がかかってしまうこともあります。
水害の影響を受けにくい住宅にするためには?
大切な命と財産を守るためにも、水害に備えた家づくりは必要不可欠です。
近年は異常気象により豪雨災害が増えているので、「これまで大雨が少ないエリアだったから」「川から離れているから」といって、水害の心配がないとは言い切れません。
水害に備える住宅づくりのポイントは、「被害をできるだけ少なくする」「被害にあったときにも復旧しやすい」の2点です。
水害の影響を受けにくい住宅にするためには、次のような家づくりが提案されています。
床の位置を高くして浸水を防ぐ
床の位置を高くして、水面が一定程度の高さになるまでは浸水しないようにする方法です。
柱などで床面を上に上げる、鉄筋コンクリート造の基礎を高くする、地盤に盛土をして地盤の高さを上げるといった方法があります。
防水壁や耐水外壁で浸水を防ぐ
耐水性のある建材(鉄筋コンクリートなど)を塀や外壁に採用して、水の侵入を防ぐ方法です。
玄関ドアや窓など開口部の隙間をなくして、そこからの浸水を防ぐこともあわせて必要です。
設備を高い位置に配置する
エアコンの室外機や給湯器といった住宅設備、コンセントなどを洪水・浸水の想定水位よりも高い位置に配置しておけば、万が一浸水した場合も被害を受けにくくなります。
修復しやすい建材の採用
断熱材を乾かせば再び使える水に強い「ウレタン系」にするといったように、修復しやすい建材を採用する方法もあります。
「FPの家」の断熱材は、水に強く経年変化がほぼない高性能なFPウレタン断熱パネルを採用しています。
サーフボードと同じ硬質ウレタン素材を使用していると思っていただければイメージしやすいかもしれませんね。
ここでひとつ、水害に強い事例をご紹介しましょう。
過去、「FPの家」の住宅展示場が豪雨被害を受け、モデルハウスが床上2mまで雨水や泥に浸ったことがありましたが、高い耐水性を持つFPウレタン断熱パネルは水害の影響をほぼ受けずに済んだというケースがありました。
周りのモデルハウスは断熱材を入れ替えるなどの大がかりな作業を余儀なくされ復旧に時間を要していましたが、「FPの家」のモデルハウスは、僅か約3週間程で原状回復に成功。
その後、5年間の展示期間を終えたあとも品質低下はなく、「モデルハウスをこのまま欲しい」といった要望に応え、断熱材であるパネルもそのまま再利用し、ユーザー宅として新たな「FPの家」に生まれ変わりました。
水害に強い「FPの家」に住むご家族の声をご紹介
水害に強い「FPの家」を新築されたお客様の事例をご紹介します。
床上浸水から直ぐに日常生活を取り戻した家
2017年10月に発生した台風21号による河川の氾濫で、とくに被害が甚大だった地域に住んでいらしたお客様。
トイレの排水口の溜まり水が逆流している状態を見たことで異変に気付き、そこから10分程度で瞬(またた)く間にドアノブの下ほどの浸水になってしまったそうです。
台風が過ぎ去ったあとは、工務店さんの協力を得ながら、水に浸ってダメになってしまった家具や家電の撤去と、室内・床下の洗浄と消毒にとりかかりました。
作業開始から3日目には、床下と室内の乾燥・消毒もおおむね終了。
10日後には家具や家電さえそろえば、また住むことができる状態まで復旧。
「同じエリアの住宅で、水害被害からどこよりも早く復旧できたのは、断熱材が水に強いFPウレタン断熱パネルだったことが一番の要因」と話します。
その後も住宅性能の劣化などはなく、快適な暮らしは変わっていないそうです。
手厚く対応してくれた工務店との出会いに感謝しつつ、「FPの家で建てて本当に良かった」と大変喜ばれている様子が印象的でした。
自身でできる水害対策もチェック!

現在住んでいる住宅で水害対策を考えるなら、まずは住宅周りに雨漏りや浸水の原因になってしまうひび割れや劣化などがないかを確認。
台風や大雨が過ぎ去ったあとも、破損がないか見ておくと良いですね。
- 外壁、屋根にひび割れ、はがれ、ずれなどの劣化がないか確認
- 雨どいに破損や詰まりがないか確認
- 窓ガラス、窓枠、雨戸に破損やひび割れ、ガタつきなどがないか確認
- 排水路に詰まりがないか確認
浸水防止に使われる「土のう」は、町内会などで配布していることも多いので、配布場所をチェックしておきましょう。
土のうがない場合は、ごみ袋やポリタンクに水を入れた「水のう」なども浸水防止に使用できます。
水のうは下水が逆流し、排水口などから水が噴き出ることを抑える効果もあります。
自宅にある身近なものを使ってできる水害対策も知っておくと良いですね。
水害に強い住宅のポイントを知って生活を守ろう
近年、異常気象の影響で毎年のように大規模な水害が起こっています。
今まで水害がなかった地域だとしても、油断は禁物。
床上浸水が発生すると、家具や家電がダメになるほか、建物そのものがダメージを受けることも多く、元の生活に戻るのに多大な労力と費用、時間がかかってしまいます。
命と財産を守るためにも水害に強い住宅であることは必須!
床の位置を高くする、浸水を防ぐ防水壁を採用する、耐水性の高い断熱材を採用するなど、できるだけ浸水被害を受けにくい、もしくは万が一被害を受けても復旧がしやすい家づくりを考えましょう。
水害に強く快適で住み良い家を建てるなら、お気軽に最寄りの「FPの家」加盟店にお気軽にお問い合わせください。
後悔のない家づくりのために、不安や疑問に分かりやすくお答えします!